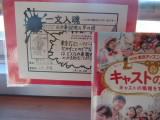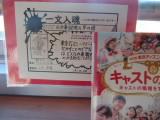行事・日々の様子(R6)
12月6日(金)「銅鐸の国」開催にあたって その2
12月6日(金)「銅鐸の国」開催にあたって その2
【銅鐸発見後の村の様子から銅鐸が買い上げられるまで】
銅鐸が発見されたことが村中に知れ渡ると、付近からの見物がひっきりなしの状況になった。また、どこからか銅鐸発見の権利を買い取りに道具屋(骨董屋)が来たという記録もある。新聞報道や豊橋市在住の豊田伊三美(珍彦)氏(豊橋趣味會会員・豊橋市編纂委員)の働きかけによって、年が明けた1月15日には元京都帝国大学教授の喜田貞吉博士(法隆寺再建論者として有名)が現地調査に訪れている。博士の調査の結果、横里富三郎さんに銅鐸を掘り出した状態で現地に据えつけてもらい、あの有名な写真(横里さんの前に3つの銅鐸が土の中から見つかった状態を写した写真:豊橋美術博物館にもその写真が展示されています)を撮影した。この11日後の26日には、京都帝大の梅原末治氏と東京帝室博物館の後藤守一氏が続いて来訪された。そして、大正15年2月7日、3個の銅鐸は1,200円(大正11年当時、お米10㎏が3円21銭、ビール大瓶1本45銭)で買い上げられ、東京帝室博物館(現在の東京国立博物館)に納められている。<1997年(平成9年)発行の「穂の国小坂井町かわら版」第6号より> 「銅鐸の国」開催にあたって その3に続く
【横里さんが銅鐸を掘り出した様子を再現したときの写真】
久しぶりに青空のもと、あいさつ運動を行いました。
12月6日(金)久しぶりに毎週のあいさつ運動が青空のもと行われました。校門の両側に立ち、小中学生が登校する両側であいさつをしている光景は毎回いいなあと思いますが、それが青空だと200%増しで素敵な光景になります。前芝の子どもたちがつくり上げてくれたすばらしい伝統です!
「銅鐸の国 伊奈銅鐸出土100年」開催にあたって その1
12月5日(木)「銅鐸の国」開催にあたって その1
豊川市教育委員会にお勤めの前田様より貴重な情報を提供していただきました。1997年(平成9年)発行の「穂の国小坂井町かわら版」第6号のコピーです。せっかくなので、生徒や保護者の皆さま、地域の皆さまにも共有したいと思い、HPで随時発信していきたいと思います。
【銅鐸発見時の様子】
今から100年前の大正13年12月22日(月)、雲一つない快晴。宝飯郡前芝村の横里富三郎さん(当時24歳)が近所の北河馨さん(あるいは親の横里豊平さん)とともに朝から小坂井村大字伊奈字松間171番地の麦畑へ大八車を引いて土砂の採掘に出かけていた。作業を始めてしばらくたった午前8時から8時半頃、横里さんが振るう鍬の先が「カチリ」と音を立てたので、そこを掘ると、地面から80cmほど下に青色の金属が砂の中から現れ、これを掘り出してみると、高さ74cmの釣鐘の形をしたものが出てきた。お昼をはさんで、午後1時前後には前芝村の林豊治さんも畑の耕作土をはねるために居合わせ、さらに北に30cm2離れたところで2個(ともに高さ80cm)見つかった。その日は3人でこの銅鐸を林さんの家へ持ち帰ることにした。<1997年(平成9年)発行の「穂の国小坂井町かわら版」第6号より> 「銅鐸の国」開催にあたって その2に続く
くしくも、この銅鐸が発見された12月22日ではないですが、およそ100年後の12月19日(木)に前芝中学校の全校生徒がその銅鐸を見学に行きます。100年前の出来事に思いを馳せながら、3つ並べられた銅鐸に何を感じてくれるのか楽しみです。
「本love推進キャンペーン」で、2年1組がどうたくんタイムに図書室へ行きました。
12月5日(木)今日は、図書委員会が企画した「本love推進キャンペーン」で、2年1組がどうたくんタイムに図書室へ行き、読書をする時間をとりました。自分の読みたい本をじっくり探す姿が印象的でした。自分の趣味の本、修学旅行で行く東京の本、好きな作家の小説など、思い思いの本を手に取り、座席に着いた後は、日々の2年生の集中力を発揮し、静かな読書タイムが始まりました。
保育園児が喜ぶおもちゃ作り(3年生家庭科)
12月3日(火) 今、3年生の家庭科では、保育園児が喜ぶおもちゃ作りに取り組んでいます。保育実習での経験を生かして、構想を練り、一人一人がフェルトを使ったおもちゃを作りました。3年2組は12月17日(水)に、3年1組は年明けに発表会を行います。
早く自分が作ったおもちゃで楽しく園児たちが遊ぶ様子を見たいですね。
喜寿苑から1年生のみなさんへメッセージが届きました。
12月3日(火)先週、1年生が喜寿苑で福祉体験学習を行いました。12月2日(月)に喜寿苑のかたが来校され、利用者のかたからのメッセージと活動写真を届けてくださいました。そこには、「若いときは可能性がいっぱいです。今を大切に過ごしてください」「明るく生活していってください」「これからも色々な事を経験してね」「カルタをして楽しかったよ。また遊びに来てね」「がんばって長生きします」「来てくれてありがとう」など、本当に心が温かくなる、そしてこれからの生き方について考えるきっかけとなる言葉ばかりが書かれていました。子どもたちもお礼のメッセージを書き、喜寿苑に届ける予定です。喜んでくれるといいです。
子どもたちにとって豊かな経験となる喜寿苑さんとの交流をこれからも続けていきたいと思います。
図書委員会の「本love推進キャンペーン」が始まりました。
12月2日(月)師走です。朝は暗く、寒くて、起きるのが辛く感じる今日この頃です。でも、今年から生徒の登校時刻がとても早くなり、寒くなってどうなるか心配していましたが、継続してがんばってくれています。保護者のかたのご協力のおかげです。本当にありがとうございます!!
今週は、図書委員会が企画した「本love推進キャンペーン」です。内容は、図書委員がお勧めする本のPOPを作成して展示したり、読みたい本の希望調査をしたりします。また、1学級ずつ朝のどうたくんタイムに図書室へ行き、読書をする時間をとります。
1日目の今日は1年1組が図書室で自分の読みたい本を探したり、友達と楽しく話しながら興味のある本を見せ合ったりしていました。また、廊下側には図書委員の作成したポップが並んでいました。どのPOPも読みたくなる工夫がしてあり、早速、そのPOPを見て、借りている人や読んでいる人がいました。POPの効果は絶大ですね。
前芝中学校は来室者が少ないと聞いているので、この機会に図書館へ足を運ぶ人、本を借りる人が増えていくといいです。
毎回テスト週間に行われる生活・学習委員会企画の「学習5原則キャンペーン」は3年1組が優勝しました。
「銅鐸の国 伊奈銅鐸出土100年」の開場式・内覧会に参加しました!
11月29日(金)今日は、豊橋美術博物館で11月30日(土)から開催される特別展「銅鐸の国 伊奈銅鐸出土100年」の開場式・内覧会に生徒代表として、生徒会長の中嶌庸介さんが参加しました。来賓として、豊橋市長、教育長、豊橋文化財センター所長、市議会議員など、多くの方々が招かれました。そして、来賓の一人として、前芝中学校、小学校からも校長の他に代表児童生徒が1名ずつ招かれました。
開場式では、大きな緊張感の中、来賓の方々と一緒に堂々とテープカットを行いました。
その後、2階の展示室へ行き、里帰りした伊奈銅鐸3点を鑑賞しました。そこへ、来賓として招待されていた京都国立博物館名誉館員で、考古学者の難波洋三先生とご一緒することができ、銅鐸の歴史や銅鐸に描かれている動物や植物の意味、銅鐸のつくりかただけでなく、考古学のおもしろさや学ぶことの楽しさなどまでご教授いただきました。児童生徒、保護者のかたとともにとても有意義な時間を過ごすことができました。
12月19日には全学年が銅鐸の鑑賞に行ってきます。銅鐸が出土した100年前、そして、銅鐸が作られた1700~1800年前に思いをはせ、郷土の歴史や文化に触れ、〝ふるさと前芝"を愛する気持ちにつながっていくといいなあと思います。
喜寿苑訪問第2弾(1年生総合)
11月28日(木)の5時間目に最後の2つのグループが喜寿苑を訪問しました。昨日訪問した生徒たちががんばってくれたおかげで、今日生徒が顔を見せると、利用者のかたがたから大歓迎を受けました。中には、中学生が今日来ることを知って、利用日を変更して来てくださったかたもいるというお話も聞きました。
最後に中学生が一人一人お礼のあいさつをした後で、利用者の代表のかたが「若い人が来てくれて本当にうれしい」と言ってくださいました。それに続いて、ほかの利用者のかたがたも「若い人はやっぱりいいねえ」と笑顔で話してくださいました。
行く前は、迷惑をかけるのではないかと不安に思うこともありましたが、子どもたちが利用者さんに笑顔で優しく接したり、遊び方を工夫してくれたりしたおかげで、利用者のかただけでなく、施設のかたにも感謝をされました。
帰る時には、玄関までお見送りに来てくださる利用者のかたもいて、子どもたちもとてもうれしそうでした。
冬休みも夏休み同様、喜寿苑でのボランティア活動を実施します。多くの生徒が参加し、利用者のかたがたの喜ぶ顔をぜひ見てほしいと思います。
1年生が総合の時間に喜寿苑を訪問しました!
11月27日(水)の5・6時間目に1年生が喜寿苑を訪問しました。今日は、6グループのうち、4グループが訪問しました。
小規模多機能ホームとグループホームに分かれて、自分たちが総合の時間に考えてきた遊びを行いました。それぞれのグループごとに「前芝の干潟かるた」やトランプ、ぬり絵、手遊びなどを行いました。大きな声で、ゆっくりと説明したり、近くまで行ってカードがよく見えるようにしたり、声をかけたりしながら、一人一人がよく考えて利用者のかたがたに喜んでもらえるように行動することができました。たくさんの笑顔を見ることができました。
いつもはあまり話さない利用者のかたが前芝出身のかたで、子どもたちが前芝中の生徒だと知ると、自分からたくさんおしゃべりしていたので驚いたと施設のかたがうれしそうに話してくれました。多くの学びがきっと子どもたちにはあったと思いますが、利用者のかたにとっても有意義な時間を過ごしてくれていたらうれしいですね。
明日、最後の2グループが訪問に行きます。その様子は明日お知らせします。
本立てを製作しています。(1年技術)
11月25日(月)今、1年生は技術の時間に本立てを製作しています。今日は、自分が作りたい大きさに木材を切るために、さしがね(L字型の定規)などを使って線を引いたり、のこぎりで切ったりしていました。自分が引いた線よりも少し大きめに切り、そのあとはベルトサンダに削っていきます。子どもたちは、慣れない機械や道具を使っての作業をいきいきと行っていました。
整美・ボランティア委員会が計画してくれた草取り&砂運びボランティア活動を行いました。
整美・ボランティア委員会の皆さんが、草取り&砂運びボランティアを計画し、全校に募集をかけてくれました。11月25日(月)の授業後に、総勢50名(1年生9名、2年生23名、3年生18名)の生徒が参加し、グループに分かれて30分間学校のためにがんばってくれました。
冬になると、前芝中学校のグラウンドの砂は強風に飛ばされ、運動場東側の側溝のあたりに降り積もってしまいます。そのせいで、グラウンドははげはげの状態です。それを今回のボランティア活動で、はげているところに砂を運び、元の状態に戻してくれました。さすが中学生です!30分間であっという間に元通りの状態になり、驚かされました。
そして、いつも地域のかたがきれいにしてくださっている慰霊碑周辺の草取りも行いました。
こういうボランティア活動が新たな前芝中学校の伝統として引き継がれていくといいですね。
避難訓練の振り返りを紹介します。
11月24日(月)今日は、先週木曜日に行った避難訓練の振り返りを紹介します。振り返りを読むと、緊張感をもってしっかりと訓練に参加していたことがわかります。避難時の話もしっかり受け止めてくれていることも伝わってきました。災害時に生きて働く力として役立ってくれることを期待しています。
〇地震が起きたら状況をしっかりと確認して行動することが大切だと考えました。相手の指示を聞いて静かに素早く行動できるように気をつけたいと思いました。(1年)
〇運動場へも若宮八幡社へもしっかり静かに避難することができました。水平避難と垂直避難のどちらかは災害時での判断であるともわかりました。(1年)
〇小学生や下級生の命を守ることも中学生の大事な役目なので、もし本当に地震などが起きたら家族や親せき、一人でも多くの命を救いたいと思いました。(1年)
〇もし前芝の人たちが全員若宮八幡社に行ったら入り切れるのか不安になりました。他にも今回行った時間で津波は来ないのか、地震などの災害の避難は垂直避難なのか水平避難なのかを見極めて行動しないといけないとわかりました。だんだん避難をするだけじゃなく、周りを助ける立場になったので、今回の避難訓練でしたことを活かしていきたいです。(2年)
〇実際に靴にはきかえるなんてことできないと思うので、石がたくさん転がっているところなどは焦らず注意して歩こうと思いました。水平に逃げるのか垂直に逃げるのかを判断するのは場合によっては自分たちかもしれないと気づいて、去年の訓練を含めて避難の仕方は理解できたので適切な判断ができるようにしたいと思いました。(2年)
〇若宮八幡社は少し遠かったけど、どこに避難をすればよいか、またどのルートから行けばよいのかわかった。また、巨大地震が来た時の備えをした方がいいと改めて理解できた。(3年)
〇先生の指示を聞き、自分で判断し、小学生を助けたりすることなどは、すべて「自分が冷静」でいることが条件であり、本番は先生を含めて誰もがその状態でいられるとは限らないので、だからこそ東北には「津波でんでんこ」という言葉があり、まず命を守ることが重要視されているんだろうなと思いました。あと、水平避難にしてもこんなにまとまって歩いている余裕はないと思うので、自分で考えて走って逃げたいなと思いました。(3年)
〇家に親がいないときのために、自分だけが家に居るときの垂直避難、水平避難場所を考えて、家族と共有することが大切だなと感じました。そして、避難をするときは津波があとどのくらいの時間で来るのかなどの情報を知ることも大切だと感じました。(3年)
〇初めての学校外への避難はとても緊張感をもって行動できました。水平避難と垂直避難でも状況によって変わったり、実際に起こらなければわからないということがわかりました。(3年)
避難訓練の水平避難で若宮八幡社まで避難しました。
11月21日(木)2学期期末テストが終わり、今日は避難訓練を行いました。巨大地震発生に伴う津波による被害を避けるために水平避難の訓練を行いました。前芝中学校にいるときには、保育園・小学校・中学校ともに、津波による被害を避けるときには若宮八幡社に避難することになっています。昨年度は、垂直避難の訓練を行っています。
今回の訓練では、水平避難と垂直避難の違いを理解し、若宮八幡社までの安全な避難経路を確認することができました。生徒たちは、真剣に訓練に参加し、若宮八幡社までの道のりも訓練という意識で歩行することができました。行きも帰りも一言もしゃべらずに黙々と歩く姿に生徒たちの意識の高さを感じました。
生徒の振り返りは、次回紹介します。
明日は「県民の日ホリデー」です。明日から三連休ですが、体調を崩すことなく、月曜日には元気な顔を見せてください。
出前講座「避難は大切ないのちづな」を行いました。
11月14日(木)今日の5時間目に「豊川」の出前講座を体育館で実施しました。豊橋河川事務所の流域治水課のかたが「避難は大切ないのちづな」というタイトルで、3つのお話(①豊川と水害を学ぶ ②河川事務所って何をしているの ③逃げるときの注意)をしてくださいました。
真剣にメモをとったり、話に耳を傾けたりしながら、防災について理解を深めることができました。生徒の振り返りを紹介します。
〇30cm水があるとうまく歩けなかったりドアが開けれなくなったりするというのも驚きました。(1年)
〇水害が危険なものだとしっかりわかりました。だからこそ、まずは逃げることを優先し、家族と事前に逃げるところ、集合するところを決めたりしたいです。逃げるときの注意にも気をつけていきたいです。(1年)
〇自分でできることをすることで自分の身を守れるんだなと感じました。そして、自分の身を守れるように気をつけていきたいと思いました。(1年)
〇豊川の水害と避難について学んでみて、下流を守るための工夫や地形や最近の降水量の特徴について学ぶことができました。防災のための知識である水位の目安や適切な靴での避難を心がけていきたいです。(2年)
〇避難した後も近所の人とのかかわりが大切なことがわかったので、普段の生活から近所付き合いを大切にし、防災について考えていきたいです。(2年)
〇今日学んだことは、雨がやんで晴れていても川は増水しているから川に近づかないこと、防災の三助、マイ・タイムラインを事前に作成することなど、たくさんのことを学びました。自分は大丈夫と思っていても全然大丈夫ではないという思いをもち、災害があったときにすぐ避難ができるようにしたいです。(3年)
〇雨が降り止んでからも増水してしまうから、雨が降り止んだからといって安心してはいけないなと思いました。(3年)
全校集会がありました。
11月14日(木)今日の6時間目に全校集会を行いました。
初めに、下水道ポスター入賞者3名の表彰、次に3年生が実施した計算コンクールと理科コンクールの表彰(最優秀賞・優秀賞・努力賞)を行いました。
次に、各委員会からの後期の活動方針について報告がありました。2年生の5名の委員長さんが委員会活動でどんな学校をつくっていきたいのか、どんなキャンペーンを行うのかを発表しました。原稿を見ずに発表する姿はとてもりっぱでした。
続いて、1月に行われる百人一首大会の連絡がありました。各学年・学級から代表者が出てきて、早押しで模擬百人一首大会を行いました。3年連続(1年生から3年生まで)のグランドチャンピオン大野さんが卒業したので、今年は全員に優勝のチャンスがあります。がんばってほしいですね。
最後は、12月19日(木)に豊橋美術博物館に銅鐸見学に行くので、銅鐸についての学習を行いました。現在は、東京国立博物館に収蔵されている伊奈銅鐸ですが、出土100周年ということで、豊橋市に戻ってきます。全校生徒でしっかり学習してきたいと思います。
メディアコントロールチャレンジの結果が出ました。
11月9日(土)に保健だよりNo.12が配付されました。内容は、第2回メディアコントロールチャレンジの結果のお知らせです。「使用時間」「寝る時刻」「寝る前ノーメディア」「目(視力)」「姿勢」の5項目でチェックしました。1回目と2回目の平均点を比較したところ、1・2年生は平均点が上がっていましたが、3年生は残念ながら下がってしまったそうです。大人も含めてメディアコントロールはなかなか難しい問題ですね。
メディアのかわりにやったこととして、「勉強」「ゆっくり過ごす」「家族と話す」「外での運動」「音楽を聴く」「本を読む」「早寝早起き」「家の手伝い」「読書」「スポーツ」「犬の散歩」「掃除」など、参考になる意見がたくさんありました。メディアの使用時間を減らして、家族と話す時間が増えたというのは素敵なことですね。
メディアコントロールチャレンジをきっかけに、家庭のルールを再確認してみてください。メディアに自分の時間や身体(視力や姿勢など)を奪われないように、自分なりのコントロール方法を身につけましょう。
テスト週間です!!
11月12日(火)今週はテスト週間です。テスト週間には、昼放課と授業後に質問タイムがあります。今日も、昼放課に3年生の教室へ行くと、廊下で数学の先生に質問している人、教室内で英語の先生に質問している人や自分で課題に取り組んでいる人がたくさんいました。受験生の教室になってきたなあと実感しました。
授業後には、1~3年生までの11名ほどが家庭科室でテスト勉強に取り組みました。わからないところを積極的に質問するなど、前向きに取り組んでいました。
以前、「中学校は努力することを学ぶ場」だという教育新聞の記事を読んだことがあります。努力したことが結果に結びつかないこともたくさんありますが、「努力する姿勢」というのは、生きていくうえでずっと役に立つことだと思います。これからも子どもたちの努力する姿勢を温かく見届けられる学校でありたいです。
今日は、全校で人権について考える道徳の授業を行いました。その授業の様子です。
勤労体験学習(資源回収)にご協力いただき、ありがとうございました。
11月9日(土)天候が心配された勤労体験学習ですが、好天に恵まれ、生徒が地域のために働く機会をいただくことができました。3時間目には通学団会を行い、仕事内容の確認と役割分担を行いました。
13時30分に各集荷場所に集合し、各地域から出された資源を生徒たちがコンテナに移し替える仕事をしました。集荷場所は、JA前芝店、高津床屋横、船だまり、加藤新田、前芝館前、宇塚公園、津波防災センター、ちびっこ広場、日色野公民館の9か所です。JA前芝店では、多くの資源が集まってきましたが、一人で2人分くらいの仕事をみんながしてくれたおかげで、時間内に終えることができました。
資源回収業者の方に、「お願いします!」「ありがとうございます!」と言える生徒がたくさんいて、とてもうれしかったです。業者の方も「いい生徒ばっかりですね」と褒めてくださいました。
PTA役員の方々やお手伝いに協力してくださった保護者の皆さん、お休みの日にもかかわらず、中学生の勤労体験学習にご協力いただき、本当にありがとうございました。そして、中学校の資源回収に協力してくださった地域の皆様、本当にありがとうございました。
寒い朝もあいさつ運動をがんばっています。
11月8日(金)生徒会執行部が1・2年生に交代し、毎週金曜日のあいさつ運動に参加する生徒も1・2年生が中心になってきました。急な冷え込みで本当に寒く、曇り空の朝でしたが、元気なあいさつで、今日もさわやかな朝を迎えることができました。
2年生男子生徒の多くが生徒会長さんの呼びかけに応え、朝早くから校門前に整列しがんばってくれています。